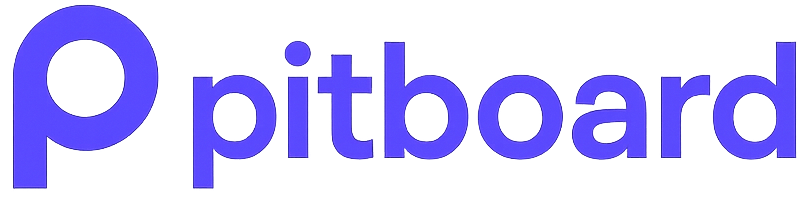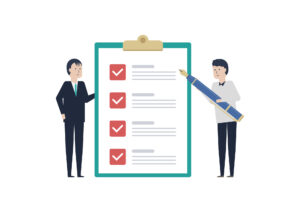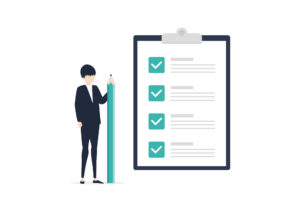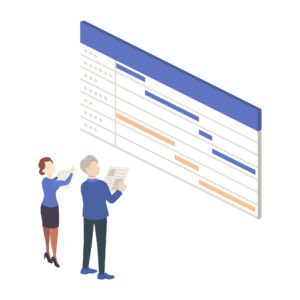ガントチャートでのタスク管理がうまくいかない5つの理由

タスク管理の手法として広く使われているガントチャート。プロジェクトの全体像や進行状況を可視化できる優れたツールですが、実際に使ってみると「運用がうまくいかない」「手間が増えただけ」という声も少なくありません。
なぜガントチャートを導入してもタスク管理がうまくいかないのか
――その原因を掘り下げ、対策までご紹介します。
ガントチャートとは?
ガントチャートは、タスクを横軸に時間軸で並べ、誰が・いつ・何をやるかを一目で把握できる管理方法です。
プロジェクト全体を俯瞰するのに適しており、WBS(Work Breakdown Structure)と並んで多くの現場で活用されています。
ガントチャートでのタスク管理がうまくいかない理由
- 計画が細かすぎて運用が破綻する
- 予測通りにタスクが進まない
- メンバーがガントチャートを見ていない
- 現場がガントチャートを「作業指示書」と誤解している
- 更新の手間がかかりすぎる
1. 計画が細かすぎて運用が破綻する
ガントチャートを精緻に作りすぎると、少しのスケジュール変更で全体を修正する必要が出てきます。その結果、更新作業が煩雑になり、「計画倒れのチャート」と化してしまいます。
対策
- 週単位やマイルストーン単位でざっくり管理する
- 日々のタスクは別ツールで管理し、ガントチャートは進行確認用と割り切る
2. 予測通りにタスクが進まない
現実のプロジェクトでは、予期せぬ遅延やトラブルがつきものです。ガントチャートは「前提としてすべて順調に進む」計画に基づくため、一度崩れると立て直しが大変です。
対策
- 余裕を持ったバッファ期間を計画に組み込む
- リスクのある工程はあらかじめ複数パターンを想定しておく
3. メンバーがガントチャートを見ていない
せっかくガントチャートを作っても、メンバーが日常的に参照しなければ意味がありません。タスク管理はチーム全員の“習慣”に落とし込むことが重要です。
対策
- 毎日の朝会などでガントチャートを確認する習慣を作る
- ガントチャートに変更があった際はSlackやチャットで通知する
4. 現場がガントチャートを「作業指示書」と誤解している
ガントチャートは「管理のための見える化ツール」であり、逐一の作業内容や工数を細かく管理するためのものではありません。過剰に細かく作成すると、逆に現場の自律性を奪う原因になります。
対策
- ガントチャートは「流れと責任者の把握」にとどめる
- 細かなタスクや日々のToDoは別ツール(例:TrelloやAsana)に分ける
5. 更新の手間がかかりすぎる
Excelなどでガントチャートを作成している場合、変更のたびに手動でバーを移動したり、日付を調整したりする必要があり、メンテナンスコストが高すぎると感じる人も多いです。
対策
- 自動更新・依存関係管理ができるツール(例:Wrike、Backlog、ClickUp)を活用する
- ガントチャートはプロジェクトの要所だけに使い、全体をシンプルに保つ
ガントチャートに向いているケース・向かないケース
向いているプロジェクト
- 長期的なスケジュールを伴う開発・建設などのプロジェクト
- 依存関係が明確で、変更が少ない業務
- 全体の進捗を可視化し、クライアントや上司に報告する必要がある場合
向かないプロジェクト
- 細かく変動する短期タスク
- アジャイル的に柔軟に動くプロジェクト
- 少人数・少タスクでスピード重視の業務
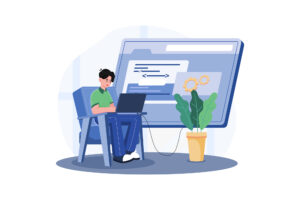
まとめ:ガントチャートは「使い方次第」で武器にも負担にもなる
ガントチャートは優れた可視化ツールですが、万能ではありません。大事なのは、「ガントチャートにプロジェクトを合わせる」のではなく、「プロジェクトに合ったガントチャートの使い方を考える」という視点です。
タスク管理がうまくいかないと感じたら、一度立ち止まって、何を可視化したいのか・どこに課題があるのかを再確認してみましょう。